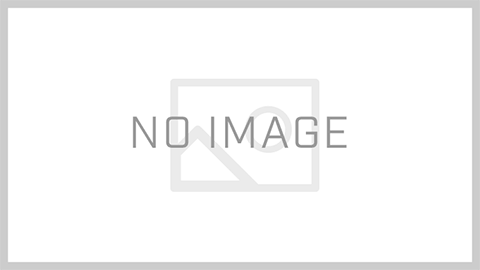定員オーバーの軽自動車が事故を起こした。と言う報道があったので、
車両における定員を超えて乗車する事の危険性を
素人ながら描いてみようと思います。
素人でもこれくらい思いつくぐらいに危ない事なんですよ
くらいに思って見ていただけると幸いです。
乗用車の定員とは
乗用車には必ず定員が設定されています。
車検証に必ず記載されていて、2人、4人、5人とか記載されています。
その車両に乗員して良い上限の人数が記載されています。
ちなみに、車検証に車両重量と車両総重量という項目があります。
車両重量は車両+燃料等走行に必要なもの+運転者(1人)の重さで、
車両総重量は車両+走行等に必要なもの+全員乗車(4人乗りなら四人分の重さ)、
を表しています。国の規定で大人一人は55kgとして計算されています。
今回の報道の事故では定員4人の軽自動車に対して、6人乗車していたと報道
されているので、国の規定に従って計算するとおよそ110kgの重量オーバーで
あると言えます。
もちろん定員数を超えたら車両の設計段階で想定している最大重量すぐにを超えるという
訳ではないと思います。4人乗りで荷物を乗せれば4人+荷物の重量となりますし、
人間の体格も様々なので、体重が40kgの人もいれば、70kgの人もいると思います。
ただ、最大の人数で乗車する、ましてや定員をオーバーして乗車(してはダメですが)
するのは、それだけの重量を車両に載せているという運転者の自覚が必要です。
重量増加の影響は?
重量が増加するとどうなるのか、素人でもわかる範囲で書いていきます。
車の基本動作、「走る、曲がる、止まる」において、
重量の増加は基本的に悪影響しか及ぼしません。
走る、加速するに関して言えば、重量増加によって速度の上昇が鈍くなるので
目標の速度になるまで、普段より多くの時間を必要とする、
アクセルペダルを普段より多く踏む必要があります。
曲がる、操舵に関しては、ハンドルを回して車が旋回を始めると車体が
普段より傾きやすくなったり、外側に膨らみやすくなります。
公道の速度制限内の速度であれば恐らくあまり影響はないと思いますが、
報道によると速度超過もしていた可能性があるとの事でしたので、
これらの影響を受けていたはずです。
そして、一番大事な止まるにおいては、減速する時の制動距離が伸びます。
制動距離とはブレーキを踏み始めて、実際に車両が停止するまでの距離です。
単純に車を止めるのにいつもより多くブレーキを踏む必要がある、
いつもより車間距離を多く取らないと危険であるということになります。
余談ではありますが、公式に行われているレースの世界でも
ハンディキャップとして、重量(バラスト)が使用されます。
つまり、車の性能を落とす(調整する)のに重量増加がどれだけ影響するのか
といったことがこの事からも見て取れます。
他にもあります。
今までは実際に車両を動かす際の動作に関する変化を主に書きました。
ここからは車両本体への負荷の話です。
まずはブレーキです。ブレーキの原理は車両の前進しているエネルギー、
運動エネルギーを摩擦によって熱に変換して放出して停止します。
(かなり雑に表現しています)
つまり、熱に対しての容量があります。もちろん、直ぐに容量がいっぱいに
なるほどギリギリの設計ではなく余裕は持たせてありますが、本来の想定を
超える負荷をかけていたとなると、話が変わってきます。
定員をオーバーして車両重量が本来の想定より重い、つまりいつもより
ブレーキを多く踏む必要がある、そして、速度が高いというのはしっかり減速
しないといけない。これらはブレーキに負荷をかけていきます。
報道では、事故の発生した道路は下り道であったとされています。
下り道ではアクセルを踏まなくでも速度が上昇してしまう場合があります、
傾斜が大きければ、車両の重量が重ければ下り坂での加速は大きくなってしまいます。
これらの要素が影響して、ブレーキに想定以上の負荷をかけてしまうと、
ブレーキの容量を超えてしまって、ブレーキの効きが悪くなる可能性があります。
最終的にはブレーキペダルを踏んでも思ったように減速しなくなり、カーブに対して
オーバースピードで侵入する事になり、非常に危険です。
次は足回りです。
主にタイヤと車体のボディを繋いでいる部分で道路の凹凸の衝撃であったり、
加速、減速、曲がりの動きに対して荷重の変化を受け止めて、ボディに緩和して
伝えるとともに、車両の姿勢が変化しても、四つのタイヤがちゃんと道路に
接している状態を作るように動いています。
これかの部品も、車両の仕様から、必要な強度であったり、可動域といったものが
計算されて設計されています。
ここに、想定外の負荷をかけてしまうと、本来の性能が発揮できなくなり、
衝撃を緩和できない、荷重の変化に対応できないといった事が起こります。
それらは、カーブを曲がった時に車のふらつき、傾きであったり、
減速時の車両の姿勢の変化が極端であったりなど、車両の動きを不安定に
してしまいます。仮に、道路の凸凹で車両の一部が跳ねてタイヤが浮いてしまったり、
カーブで傾いてしまっている時は、浮いたタイヤ、傾いた内側のタイヤは道路に
接していない、または浮く一歩手前なので本来のグリップ力を発揮できず、
曲がりの性能を著しく低下させてしまいます。
恐らく、事故に直結するであろう部分は大きくこの二つだと思います。
最後に
車は便利で楽しい、乗り物、移動手段ですが
およそ1トン以上の鉄の塊です。
日常的に目にして、利用するものなので、危機感が無いかもしれませんが、
一歩間違えば、相手や自分の命を簡単に奪うものであることは変わりません。
自動車メーカーが安全や性能を保証できるのは、仕様を守って、
ちゃんとメンテナンスしている車両のみです。
使用者の都合で仕様を無視して好き勝手に動かしたものについては、
とても保証などできません。
そもそも、仕様を守っていたとしても、安全運転を心がけていなければ、
いつ事故が起きてもおかしく無いのです。
一歩間違えば、車は人の命を奪うものである。
という自覚を持って運転する必要があります。